ベーム式
-
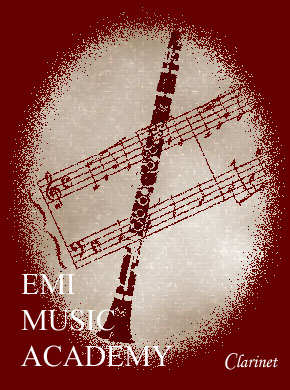
もっとも一般的なのが、ベーム式(フランス式)クラリネットのキー・システムである。
1843年にフランスのルイ=オーギュスト・ビュッフェ(L. A. Buffet1885年没)とイアサント・エレオノール・クローゼ(H. E. Klose1808年-1880年)によって、ベーム式フルートのキー・システムを応用して1844年に特許申請し開発された。
管弦楽、吹奏楽、ジャズなどで広く用いられている。
キー・システムの機構は複雑になってしまうが、比較的単純な運指が実現でき、機動性が高い。
初心者にも向いている。
エーラー式
-

ドイツ式のエーラー式クラリネットは、1812年にミュラー(I. Muller)が開発した13キーのクラリネットを元に、ベーム式クラリネットが発明された約60年後(※1)にオスカール・エーラーによって開発された。
ベーム式クラリネットの利点も取り入れられている。
エーラー式クラリネットにも音色のよさから愛好家は多い。
また、特にドイツ人のクラシック演奏者はエーラー式クラリネットを好んで使っている。
(※1)日本ではエーラー式をもとにベーム式が作られたという間違った解釈がまれに見受けられるが、これは大きな間違いである。
なぜならエーラー式を開発したオスカール・エーラーが生まれたのは1855年でベーム式が生まれた1839年頃にはまだ生まれていないからである。
また、ベーム式はドイツ式の亜種という意見も稀に見受けられるがこれは不適当な意見である。
ベーム式クラリネットは独自に開発されたものという解釈が適当であろう。
ベーム式によってフランスでは多くの小品やソナタが生まれた。
そのほかのキー・システム
-
また、オーストリアではウィーンアカデミー式という楽器が使用されている。
アルバート式のキー・システムは最近はあまり用いられていない。
音色はベーム式やエーラー式とは明らかに異なる。
もともとはクラシックでも使われていたらしいが、ベーム式やエーラー式のクラリネットに混じって演奏すると目立ってしまう。
また、大きな音量が出る。
アルバート式のクラリネットは、ニューオーリンズ・ジャズ、ディキシーランド・ジャズといった古いスタイルのジャズを演奏するときによく用いられた。
現在でも古いスタイルで演奏するときに用いられることがある。
リフォームド・ベームとは、エーラー式キー・システム用に設計された管に、ベーム式キー・システムを実装したクラリネットである。
エーラー式の音色のよさとベーム式の機動性ある運指とを兼ね備えている。

